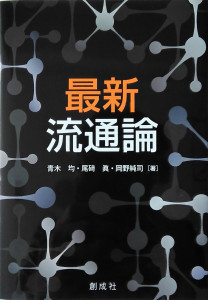-
最近の投稿
アーカイブ
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
カテゴリー
カテゴリー別アーカイブ: 教員
新任教員の紹介(1)
商学部では本年4月に2名の新任教員を迎えましたので、ご紹介をいたします。
まずは、橋本理博准教授(金融論)をご紹介いたします。
出身地:岐阜県
専門分野:金融論、経済史
主な業績:
・「アムステルダム銀行の預金受領証は『銀行券』だったのか―受領証の性格が映し出す銀行券と銀行預金の同一性」『法と経営研究』第2号、2019年1月、103-121頁。
・「損害保険会社の社員の金融リテラシーと金融教育の課題―2018年と2019年の調査結果を中心にして―」(共著:家森信善)『損害保険研究』第82巻第3号、2020年11月、1-34頁。
最終学歴:
名古屋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了
就任直前の職歴:
名古屋経済大学経済学部准教授
趣味・スポーツ:
息子(3歳)と遊ぶこと
就任の挨拶:
今年度より商学部で金融関連科目を担当させて頂きます。皆さんと共に学ぶことを楽しみにしています。どうぞ宜しくお願い致します。
http://comm.agu.ac.jp/teachers/teachers/hashimoto/index.html
学部長便り⑦
4月1日に入学し、7日から授業が始まりました。新入生の皆さんは慣れないことばかりで、4月いっぱいは疲労困憊かもしれません。大学に慣れてきた頃に、大学で何をすべきなのかよく考えてください。
大学というところは、教育機関でありながら、研究機関でもあります。
われわれ教員が研究者として研究活動に従事するのはもちろん、学生も教員の研究の一端に触れ、手ほどきを受けながら研究を手掛けることが求められています。
研究というのは、分からないことを分かろうとする営みです。
社会現象において、いまだに解明されていないことがたくさんあります。
分からないことだらけといっても過言ではありません。
新入生の皆さんも素朴な疑問を大事にして、「なぜこのようなことが起きるのか、自分なりに答えを出してみよう」という姿勢で、大学生活を送ってください。
その姿勢が皆さんの頭脳を鍛え、変化に適応する能力を養うことになります。
文責:青木
新任教員着任のお知らせ
愛知学院大学商学部において、今年度新任教員として橋本理博准教授(金融論)と李 素煕講師(流通論)が着任しました。
教員紹介ページも、2021年度版に改訂いたしました。
対面授業再開
愛知学院大学では、9月21日(月)より秋学期の授業が開始しました。
商学部では実習を伴う科目や演習科目など一部の科目で、学内での対面授業が再開されました。
学生からは
「友達や先生から直接教えてもらえて、コミュニケーションをとることができて良かった」
「周りに一緒に受ける学生がいるので、モチベーションが上がった」
などの声を聴くことができました。
一方で
「コロナの影響で通学が不安である」
との意見もありましたが、愛知学院大学では感染拡大防止の観点から、秋学期は対面授業においても通学困難な学生に向けてオンライン(Teamsなど)での授業コンテンツの公開を続けていきます。
学部長便り⑤
商学部では、9月21日(月)より秋学期の授業が始まります。
春学期中は商学部の授業は全て基本的に遠隔授業でしたが、秋学期は、演習、実習、語学の一部について、対面授業を実施します。
今年3月に名城公園キャンパスは拡張工事を終え、完成しました。全商学部生には、いよいよこのキャンパスに通ってもらえます。
遠隔授業は残りますので、通学機会は限定されますが、1年生には、ようやく大学生らしいキャンパスライフを送ってもらえると思います。
また、2年生以上の学生にも、半年ぶりにキャンパスでの学びを味わってもらえます。
キャンパスの各施設では、新型コロナウイルスの感染防止対策をとっています。
学生の皆さんもマスクや手洗いなどの対策をして、通ってきてください。
また、通学に不安がある学生は、遠隔でも授業が受けられるよう各教員が対応しますので、安心してください。
文責:青木
ビジネス科学研究所発足
産業研究所と流通科学研究所が合併し、4月1日よりビジネス科学研究所が発足されました。
所長に城隆教授(前流通科学研究所長)が就任しました。
前産業研究所長の田畑康人教授は、4月に新設された愛知学院大学社会科学研究センター長に就任しました。
新教務主任のお知らせ
松本力也教務主任が3月31日をもって任期満了となったのに伴い、4月1日付で岡野純司准教授が商学部教務主任に就任しました。
新入生の皆さんへ(学部長挨拶)
新入生の皆さんの入学をお祝いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は入学式を挙行できません。皆さんは大学生活のスタートを彩る式典に参加できず、残念な気持ちでいっぱいだと思います。いつもは、入学式当日に、皆さんに加え保護者の方々を前に、学部長挨拶を行うのですが、今年度はそれが叶いませんので、その代わりに、ここに挨拶文を掲載いたします。ここでは、皆さんにどのように学生生活を送って欲しいのか、私なりの考えを述べて挨拶といたします。
まず、皆さんが生まれた年に思いをはせてください。皆さんのほとんどは2001年前後に生まれたと思います。2001年はどういう年だったのか少し振り返ってみます。
この年、アメリカにおいて同時多発テロが起きました。ニューヨークの世界貿易センタービルに飛行機が衝突して、ビルが崩れ去りました。それに対して、アメリカ軍はアフガニスタンに侵攻しました。
日本においては、この年、中央省庁再編が行われました。その結果、厚生労働省や国土交通省などが生まれました。また、小泉純一郎さんが首相になり、小泉政権による「聖域なき構造改革」が日本中で話題になり、流行語にさえなりました。
経済面では、大阪にUSJが誕生しました。さらに東京ディズニーランドにディズニーシーが併設されました、本格的なテーマパーク競争時代が到来しました。ブロードバンドという言葉が登場し、ヤフーなどが有線による高速通信サービスを提供しました。本格的なネットビジネスの時代を迎えました。また、JR東日本が電子マネーSUICAを導入し、ようやく電子マネーの普及が始まりました。雇用面では、求人倍率は0.6程度と低くて、就職活動に苦労する学生が多く、就職氷河期という言葉が頻繁に使われました。
愛知学院大学商学部がこの年どういう状況にあったかというと、キャンパスは日進市にあり、商学科と産業情報学科の2学科体制、1学年の定員は550名でした。
あれから20年近く経ち、私たちの生活はどうなったでしょうか? 2001年当時インターネットはまだ特別な存在で、パソコンを利用して有線で接続していましたが、今ではスマートフォンが普及し、スマートフォンを使って無線で接続して、ゲームをしたり、買い物をしたり、メールを送受信したりするようになりました。電子マネーは今や当たり前の存在になり、バーコード決済など新種のキャッシュレス決済も私たちは活用しています。
この商学部をとりまく環境はどうなったでしょうか? 日進キャンパスから全面的に名城公園キャンパスに移転しました。この4月から全ての商学部学生が名城公園キャンパスで学ぶことになりました。現在学科は商学科1学科のみ。1学年の定員は250名です。キャンパス、学科、カリキュラム、定員など全く変わってしまっています。
こういう状況を踏まえて、新入生の皆さんがこの先4年間何をすべきなのか。これから皆さんが生きていく世界は、これまでと同様かこれまで以上に変化が激しいと考えてください。したがって、激しい変化に対応できる人材にならないと職業人として生き残っていくことは難しいでしょう。大学在籍中、変化に対応できる力の基盤を作り上げてください。
そのためには、どうすればよいのでしょうか?
大学には、中学や高校あるいは専門学校とは違う、際立った特長があります。それは、教育と研究が一体化している点です。研究とは、未知の事柄に対して、自分なりに答えを見つけ出す努力を指します。そのため、まず世の中で解明されていない事柄や現状の問題を見つけ出す必要があります。つぎに、それに対して、解決案の導出に向けて試行錯誤することが求められます。大学では、教員がリードして、この営みに学生を巻き込んで教育を進めるのです。教員が定まった答えを伝授し、それを学生に覚えこませることは大学教育の本質とはいえません。
皆さんは、拙いながらもその研究に積極的に取り組んでいくことによって、変化適応力の基盤が形成されます。変化の激しい時代、とくに経済においては、定まった答えなど存続しえません。答えはすぐさま古びてしまいます。したがって、自分なりに問題を見つけ出して、解決案を考察しなければならないのです。大学において、研究に巻き込まれれば、自分なりに問題を見つけ出して、解決案をひねり出すために試行錯誤する習性が身につきます。これこそが変化に対応できる力の基盤なのです。商学部では演習と呼ばれる科目を中心に、学生を研究に巻き込む教育が展開されています。例えば、なぜ今日本では人手不足なのに賃金が上がらないのか、どうすればアマゾンに対抗して小売店は生き残っていけるのか、このような疑問に自分なりに答えを出してください。
また、幅広い教養を身につけことも心がけてください。この先どのような分野が社会の主流になるのか、だれにも予想できません。どんな知識が将来重視されるのか確実な予想は存在しません。したがって、どんなことにも対応できるように、知識の引き出しを少しでも多く持つ必要があります。これもまた変化適応力の基盤なのです。
商学部長 青木 均