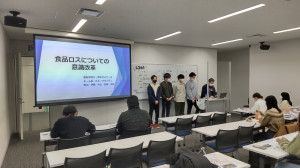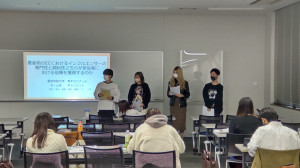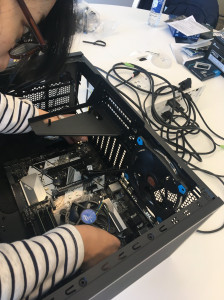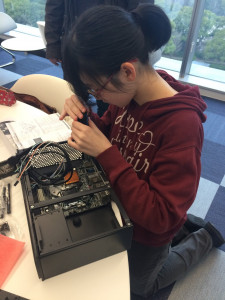こんにちは。商学部の教員の李素煕です。
今回は「応用商学Ⅹ(海外の消費市場と消費者を学ぶ)」について紹介します。
近年の日本の消費財メーカーは、海外での販売抜きにその成長が語れないほど、海外市場への依存 度が高くなっています。
昨今はコロナの影響で訪日観光客が減っていますが、今や日本の観光地も 海外からの観光客を抜きにビジネスが成り立たなくなっていることは承知のごとくです。
しかし、海外の市場では日本でヒットした商品がまったく売れなかったり、思わぬ商品が人気にな ったりしています。
観光地にしても、予想もしなかったスポットに外国人が殺到する現象があちこ ちで生じています。
なぜ、このような現象が生じるのでしょうか。
実は、この現象の裏側には日本と海外での「暗黙知」の異なりが存在しています。
同じ商品を見ても、 同じ色を見ても、同じデザインを見ても、同じ商品名を聞いても、日本人、中国人、アメリカ人、フラ ンス人では、それらから受けるイメージや感じ方が大きく異なることが分かっています。
何が「美しい」のか、何か「かっこよい(おしゃれな)」のか、何が「使いやすい(機能的な)」のか、 何が「かわいらしさを感じさせるネーミング」なのかは、世界の国や地域によって大きく異なることが あります。
観光地も同じで、出身国によって「魅力的」に感じるポイント、つまり風景や文化財が持つ 「意味」が異なるため、人気のあるエリアに違いが生じているのです。
このような感じ方の違いは、個人差に起因する面もありますが、国や地域ごとに共有されている感じ方の 違いに起因している面もあります。
たとえば、金色を見たときに、日本人は「豪華さ」を感じる反面、「成 金」「派手」などとネガティブな印象も持ちます。
しかし、中国の人は「縁起が良い」「清らか(邪気を払う)」と感じることが多いとされます。
このような国や地域ごとに異なる「規範感覚」の違いのことを「地域暗黙知」と呼びます。
応用商学Ⅹでは、海外の消費者の消費行動の背後にあるローカルな「暗黙知」を理解し、適切なマーケティング戦略のあり方を受講生の皆さんと一緒に考えます。