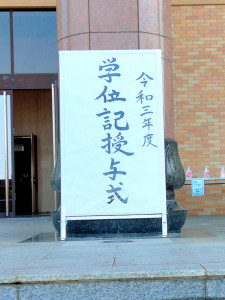-
最近の投稿
アーカイブ
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
カテゴリー
カテゴリー別アーカイブ: 教育
商学部の専門科目紹介:応用商学ⅩⅤ (SDGsと企業のCSRマネジメント)
お久しぶりです♡ しのっちこと、商学部の志野です。
前回の経営管理論の紹介はいかがでしたか。
今回の私の担当する科目の紹介ですが、昨年度から始めた、応用商学ⅩⅤ(SDGsと企業のCSRマネジメント)についてお話します。
みなさんもご存じの通り、SDGsとは、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)のことです。
これは、国連が2015年に国連サミットで採択した世界各国が取り組むべき目標で、17個(169ターゲット)が設定されています。
これが提唱された2015年当時は、誰もこれに見向きもしませんでした。
それどころか、フリーメイソンの陰謀説が唱えられ、さらに元アメリカ合衆国大統領のドナルド・J・トランプが、自国優先主義を唱えた結果、各国もそれに倣ったような風潮が出来上がり、マスコミのみならず、学校教育の現場でも知らない人が多数を占めていました。
私も恥ずかしながら、これを知ったのは、2017年頃に、タレントのピコ太郎が、外務省の動画の中で、SDGsをプロモーションした踊りを公開し、それを講義の中で偶然見た時に、はじめてSDGsの存在を知りました。
その後、経営学Bで、CSR(企業の社会的責任)を教えているのですが、企業のCSRの紹介サイトが、徐々にSDGsのレインボー色に染められていきました。
その背景には、2017年11月に経団連の企業行動憲章が改訂され、SDGsの達成が優先事項として取り入れられたことが、最大の原因だと考えられます。
そして、今や、企業のCSRは、SDGsを切り離しては考えられなくなっています。
その後、企業の積極的なSDGsの取り組みへとつながっていき、今や、SDGsはあらゆるメディアで報じられるようになりました。
日々のニュースから娯楽番組に至るまで、SDGsを見ない日は、ほとんどありません。
これを見ると、いかに私たちの日本社会が、企業によってコントロールされているかがわかります。
さて、昨年度から始まった応用商学ⅩⅤ(SDGsと企業のCSRマネジメント)ですが、17の目標の中で、受講者が選択したテーマは、どのようなものだったでしょうか。
春学期と秋学期の受講者の学期末レポートのテーマの内訳のベスト5は、以下のようになりました。
第1位 目標6「安全な水とトイレを世界中に」9名
第2位 目標14「海の豊かさを守ろう」7名
第3位 目標15「陸の豊かさを守ろう」6名
第4位 目標4「質の高い教育をみんなに」5名
第5位 目標1「貧困をなくそう」4名
残念ながら、商学部に関係するであろう、目標12「つくる責任、つかう責任」を選択した学生は2名に過ぎませんでした。
やはり、近年の地球温暖化や森林破壊、海洋汚染などに関心のある学生が多いのが特徴です。
ただ驚いたのが、目標1の「貧困問題をなくそう」を選んだ人が4名もいたことです。
その学生のレポートの中で、「僕が目標1を選んだのが、多くのSDGsの問題の発端が貧困問題と関係しているから、このテーマを選んだ」と書かれていました。
また、第一位の目標6「安全な水とトイレを世界中に」を選んだ学生の多くは、水資源が豊富で、水道水をそのまま飲める日本の素晴らしさを讃えていました。
以上のように、昨年度からはじめた応用商学ⅩⅤ (SDGsと企業のCSRマネジメント)では、私も知らないことばかりです。
私の専門外のことも出てきました。
おそらく学生の皆さんの方が知識のあるテーマもあるでしょう。
今後も、お互い、ほどほどに、楽しみながら、学び合い、許し合いながら、進めていきたいと思います。
例えば、SDGsの表現のパロディですが、高齢夫婦を笑いのネタにする芸人の綾小路きみまろは、SDGsを次のように言い換えていました。
「少し(S)、ダメでも(D)、我慢(G)、する(S)、という心構えこそが、持続可能な夫婦生活の秘訣である」、とです。
私の担当する応用商学も、この精神で進めていきたいと思っています。
第7回 ビジネスカンファレンスが開催されました
商学部主催の第7回ビジネスカンファレンス(通称、ビジカン)が今年度も開催されました。
今年度は、愛知学院大学商経会様協賛のもと実施されビジカンでした。
ビジカンは、昨年度に引き続き、今年度も論文セッションと、15分の動画を用いたプレゼンセッションの2セッションが行われました。
論文セッションには、商学部から19本の論文がエントリーされ、プレゼンセッションには、商学部、経営学部および経済学部から63報告がエントリーされました。
オリジナリティに溢れ、論理的一貫性のある論文や報告が多く、コロナ禍であっても各学生がしっかりとした研究を行っていることをうかがい知れました。
各論文および報告を審査し、各セッションの評価を行いました。
各コース別の最優秀研究賞(プレゼンセッション1位)と最優秀論文賞(論文セッション1位)は以下のとおりです。
◆ 最優秀論文賞
◎ 流通・マーケティングコース
吉田和磨(青木ゼミ・商学部4年)「高校生が学習塾を選択する上での要因」
◎ 会計・金融コース
中嶋愛由美(野口ゼミ・商学部4年)「のれんの事後測定に関する研究」
◎ ビジネス情報コース
宮澤怜那(吉田ゼミ・商学部4年)「学校運営のためのRPAの活用に関する研究」
◆ 最優秀プレゼン賞
◎ 流通・マーケティングコースおよびビジネス情報コース
加藤芙巳奈(秋本ゼミ・商学部4年)「株式会社フィールコーポレーションにおけるマーケティング戦略」
◎ 会計・金融コース
中嶋愛由美(野口ゼミ・商学部4年)「のれんの事後測定に関する研究」
上記以外にも、優秀論文賞や優秀プレゼン賞等が、素晴らしい論文やプレゼンに対して授与されました。
詳細は、下記リンクよりご参照下さい。
第7回ビジカン表彰者一覧
来年度は今年度よりもレベルの高いビジカンになることを祈念しております。
最後になりますが、ご協賛下さいました愛知学院大学商経会様に心より感謝申し上げます。
商学部の専門科目紹介:応用商学Ⅶ(国際ビジネス)
今回は、商学部の専門科目「応用商学Ⅶ(国際ビジネス)」を紹介します。
応用商学は学生が自分で取り組んでいく実用的な科目であり、自分で調べて発表することによって理解を深めることができます。
応用商学には各分野から多様な領域がありますが、そのなかで国際ビジネスというと英語が関係するのかとか、私の生活には関係ないとか考える人もいるかもしれませんが、世界の国々で国際ビジネスと無縁でいる国は皆無と言っていいと思います。
言い換えれば、企業が行う貿易や外国での活動は、国家経済の成長の源泉の一つです。
身近な例としては、君たちの衣食住の主だったところは国際ビジネスによって維持されています。
担当する梶浦教授が編集執筆した教科書を用います。
この本で商学部や経営学部などの大学生諸君、経験の浅いビジネス・パーソンはグローバル・ビジネスとマーケティングの基本戦略を学んでいただけます。
その内容は、多国籍企業が世界市場に参入する際の企業戦略、競争戦略、マーケティング戦略を解説するものです。
これらについて基本内容から始め、やや専門的内容までを包括しています。
梶浦教授は、日本の食品企業大手に勤務後、欧州に本社のあるグローバル企業2 社に奉職した時期があり、現在も企業関連団体で役職を務めております。
実務経験はもとより、執筆者諸氏の企業経験や社会経験も随所に盛り込まれています。
調査や発表を通じて役立つ経験にもなるだろうと思いますので、履修されてはと思います。
商学部の専門科目紹介:Webデザイン
皆さんこんにちは。商学部ウェブサイトへようこそ。
商学部教員の笠置です。
今回は、商学部の専門科目「Webデザイン」について紹介します。
社会では、インターネットを利用した情報発信ツール(電子メールやブログ、電子掲示板、SNS、…など)が溢れています。中でも、不特定多数に多くの情報を発信するホームページ(Webサイト)の構築は、工夫次第でさまざまな表現をすることが可能です。
本ブログを見ている“あなた”ならば、基本を学べば必ずWebサイトを作成することができます!! Webサイトを作成したことが無く、基本を知らないから抵抗があるだけです。まずは難しいと考えず、興味を持って一歩踏み出してみましょう。
【Webサイトを公開するまでの流れ】(概略)
Webサイトを運用するためには、はじめに①計画(立案、素材(画像や文章)の準備)し、次に②デザイン(レイアウト、Webページの内部リンク、他サイトの外部リンク)を具体的に考え、③コーディング(HTML、CSS)を行い、必要に応じてプログラミング(Java、PHP等)を行う。さいごに④インターネットに公開する。④で完成ではなく、不具合や改善を繰り返して⑤Webサイトを保守・管理・アップデートします。
Webサイトを作成する場合、ターゲットに情報をどのように発信するのかを考え、“どのようなレイアウトで作成するべきなのか?”や“配色をどうするべきか?”、“図表の大きさはどれ位にするべきなのか?”など考える必要があります。
本科目では、HTMLおよびCSSの基礎を学び、Webサイトを制作(実習)し、発表会を通じてフィードバックするなど、さまざまなWebデザインについて提案できる人材を育成します。特に、商学部ではe-コマースを考えたWebデザインや、広告デザイン、プレゼンテーションなどを想定した学びを実現しています。
Webデザインが分かると世界が広がります!興味がある人は、ぜひ愛知学院大学商学部でお待ちしております。
商学部の専門科目紹介:流通政策
今回は商学部の専門科目、流通政策について紹介します。
わが国では1980年代以降、規制緩和(規制改革)が本格的に取り組まれるようになりました。
規制緩和とは、企業の経済活動に対する政府のさまざまな規制を廃止・緩和することです。
その目的は、市場における企業間の競争を促進し、企業の経済活動を活性化するためです。
この規制緩和は流通分野でも積極的に行われ、これらに大きな変化をもたらしました。
一例を挙げれば、中小規模の小売業者を守るためにスーパーなど大型店の出店を制限する大規模小売店舗法という法律が緩和・廃止されましたが、この結果、各地で大型店の加速度的な出店や商店街の衰退をもたらしました。
医薬品流通における規制緩和は、薬局だけでなく、コンビニエンスストアやインターネット通販など多様な小売業者で市販薬が購入できるようになるという変化をもたらしました。
流通分野における規制緩和の進展により、消費者は,良質な商品を低価格かつ高サービスで入手することができるようになり、あるいは買物の利便性を享受することができるようになりました。
しかし、商店街のシャッター化などにより買い物が不便になる人々も生まれました。
小売業者にとっても事業が成長する機会を得ることになった反面、小売業者間の競争激化にさらされるようになりました。
この授業では、このように流通に大きな影響力を持つ流通政策について、その概要や競争政策(市場における競争を維持・促進する政策)、振興政策(中小流通業者の事業活動を支援する政策)、商業まちづくり政策(中心市街地において商業を含む街づくりを促進する政策)などに焦点を当てて、1年間を通して学びます。
皆さんが将来メーカーや流通企業に就職し、日々のビジネスを行う際に、流通政策の適用を受ける場面も多いです。
これらの企業でビジネスを行いたいと考えている方は、ぜひこの授業を履修してみてください。
商学部の専門科目紹介:応用商学Ⅹ
こんにちは。商学部の教員の李素煕です。
今回は「応用商学Ⅹ(海外の消費市場と消費者を学ぶ)」について紹介します。
近年の日本の消費財メーカーは、海外での販売抜きにその成長が語れないほど、海外市場への依存 度が高くなっています。
昨今はコロナの影響で訪日観光客が減っていますが、今や日本の観光地も 海外からの観光客を抜きにビジネスが成り立たなくなっていることは承知のごとくです。
しかし、海外の市場では日本でヒットした商品がまったく売れなかったり、思わぬ商品が人気にな ったりしています。
観光地にしても、予想もしなかったスポットに外国人が殺到する現象があちこ ちで生じています。
なぜ、このような現象が生じるのでしょうか。
実は、この現象の裏側には日本と海外での「暗黙知」の異なりが存在しています。
同じ商品を見ても、 同じ色を見ても、同じデザインを見ても、同じ商品名を聞いても、日本人、中国人、アメリカ人、フラ ンス人では、それらから受けるイメージや感じ方が大きく異なることが分かっています。
何が「美しい」のか、何か「かっこよい(おしゃれな)」のか、何が「使いやすい(機能的な)」のか、 何が「かわいらしさを感じさせるネーミング」なのかは、世界の国や地域によって大きく異なることが あります。
観光地も同じで、出身国によって「魅力的」に感じるポイント、つまり風景や文化財が持つ 「意味」が異なるため、人気のあるエリアに違いが生じているのです。
このような感じ方の違いは、個人差に起因する面もありますが、国や地域ごとに共有されている感じ方の 違いに起因している面もあります。
たとえば、金色を見たときに、日本人は「豪華さ」を感じる反面、「成 金」「派手」などとネガティブな印象も持ちます。
しかし、中国の人は「縁起が良い」「清らか(邪気を払う)」と感じることが多いとされます。
このような国や地域ごとに異なる「規範感覚」の違いのことを「地域暗黙知」と呼びます。
応用商学Ⅹでは、海外の消費者の消費行動の背後にあるローカルな「暗黙知」を理解し、適切なマーケティング戦略のあり方を受講生の皆さんと一緒に考えます。